0.1秒後に、どのくらいまで加速/減速しているのかは、車体重量と「力」の大きさから計算することができます。

ドローム用シミュレーションシステムについての簡単な説明
計算の方法はそんなに難しいものではありません。
ある瞬間の車体の状態(速度など)を考え、次の瞬間、たとえば0.1秒後の状態を推測し、これを繰り返すことでコース周回分の走行の状態を推測する、という方法です。
たとえば、ある瞬間80km/hの速度でストレートを走行している状態を考えてみます。
0.1秒後の速度はどうなっているでしょうか?
もし、進行方向前方に「押し出す」力が働いていれば80km/hより速いスピードへと加速しますし、逆に後方へと「引っぱる」力がはたらいていれば減速します。
0.1秒後に、どのくらいまで加速/減速しているのかは、車体重量と「力」の大きさから計算することができます。

では、どのようにしたら力の向きと大きさがわかるでしょうか?
車体に働く力を3つに分けて考えてみます。
(1)モーターによる推進力
車体を前に押し出す力です。モーターは、速く回るほど力(トルク)が弱くなる性質を持っています。
ある時点での速度(たとえば80km/h)に、ギア比やタイヤ径を掛け合わせればモーターの回転数がわかりますから、それからトルクを推測します。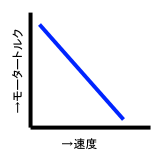 モーターの回転数とトルクの関係はグラフにすると直線関係であわらされ、その直線を調べる、つまりどのくらいの回転数のときにどのくらいのトルクが出るのか、といったことを実際のモーターで測定するのがモーターダイノです。今回のデータはすべて宮谷さんに測定していただいたものです。
モーターの回転数とトルクの関係はグラフにすると直線関係であわらされ、その直線を調べる、つまりどのくらいの回転数のときにどのくらいのトルクが出るのか、といったことを実際のモーターで測定するのがモーターダイノです。今回のデータはすべて宮谷さんに測定していただいたものです。
(2)空気抵抗
走行中の車体を後ろへ引っ張る力、つまり抵抗力です。
空気抵抗は、
i)車体速度
ii)ボディの前面投影面積
iii)ボディの空気抵抗係数(CD値)
によって大きさの決まる力です。
ドロームほどのスピードになると、空気抵抗は300g以上もの大きさになるようです。
(3)ころがり抵抗
これも走行中の車体を後ろへ引っ張る力です。
この力のほとんどはタイヤと路面の摩擦力に起因するものです。
一般的に、この力は速度によってあまり影響されない力です。以前実測を試みたことがあります。
ただし、車体垂直にかかる力に比例する力なので、バンクにおいて「縦G」が2倍になればこの値も2倍になります。
バンクコースにおいては、ころがり抵抗が変化することにより、常時フルスロットル走行であるにもかかわらず、速度の増減が起こります。
以上の3つの力を合計したもの、
(推進力)−(空気抵抗)−(ころがり抵抗)
が車体進行方向にはたらく力になります。これがプラスだったら加速、マイナスだったら減速することになります。
この値が0の点では、推進力と抵抗力がつりあっている状態で、そのときの速度が最高速度になります。
0.1秒後の速度がわかれば、そのあいだにどのくらい車体が進んだか、コースのどの位置にいるのか、その地点でのバンク角は何度か、コーナリング遠心力は、縦Gは、などを順次計算することができます。
このような計算を順次繰り返し、コース周回のシミュレーションとしているのです。